仏教エンタメ
仏教エンタメ2026/01/20ツイート
仏教の文学3『たけくらべ』樋口一葉著
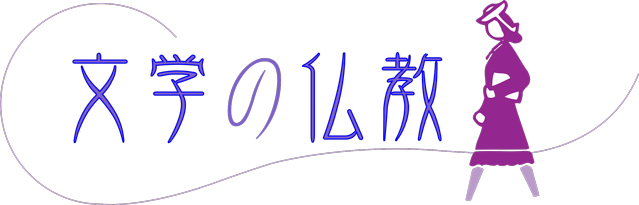
『たけくらべ』樋口一葉著
 なまじ文学史に残るような名作だったばっかりに、中学生くらいの時に教科書で読まされて、内容もよく分からず、そのままになってしまった小説ってないだろうか。『たけくらべ』は、おおかたの人にとって、まさにそういうものではないかと思う。
なまじ文学史に残るような名作だったばっかりに、中学生くらいの時に教科書で読まされて、内容もよく分からず、そのままになってしまった小説ってないだろうか。『たけくらべ』は、おおかたの人にとって、まさにそういうものではないかと思う。
実際のところ、あるていど大人になってからでなければ、この小説の意味も内容も、じゅうぶんには理解出来ないだろう。いくら登場人物たちが十五、六歳の少年少女であるにしても、読む方が同年輩だからといってより深く理解出来るということでもあるまい。むしろ、すでに大人になってしまった人間が読んだときこそ、この小説の意味というのがずしんと胸にこたえてくるのだ。
『たけくらべ』というのは、たいていの青春ドラマがそうであるように、「別離」の物語なのである。「あのときは、あんなに一緒だった」という甘さ。
「だけど今はこんなに離ればなれになっていく」という哀しさ。そして、この物語の中でもっとも鮮やかに離れていくのが「何がしの学林に袖の色かへぬべき」寺の息子、龍華寺の信如なのである。
この物語の主筋が信如と、大黒屋の美登利の淡い初恋にあることは間違いない。寺の息子と遊郭の少女。こう書くととてつもなく隔たった境遇のようだが、長い物語をゆっくり読み進んでいくと案外そうでもないのだ。二人は同じ私立学校にかよう同級生でもあるし、美登利の方は物語の終盤まで、いずれは遊女になるしかない自分の境遇にまったく屈託を抱いていない。屈託があるのはむしろ信如の方で、しかもそれは父である住職のありようから出ているのである。
信如の母である妻を娶るときも、「経済より割出しての御不憫かかり」というくらい徹底した現実主義者であるこの父親は、「朝念仏に夕勘定、そろばん手にしてにこにこ」。檀務のかたわら娘には葉茶屋を、妻には簪の店をやらせ、スタミナ不足は好物の蒲焼と泡盛で補うというやり手。一葉の筆はそれを良いとも悪いとも言っていないが、信如からすれば「何故その頭は丸め給ひしぞ」と恨めしく恥ずかしく、ために彼は異常なまでに人の目を気にする少年として造形されている。彼にとっては、美登利が向けてくるまっすぐな好意さえもひたすら恐ろしく、身の縮む思いがするばかりなのである。
ラストシーンでは、信如がどこか遠くの宗門道場に旅立ったことが示唆される。「別離」の印象が鮮やかに伝わってくる、切ない幕切れだ。しかし考えてみれば、これは彼が正式に僧侶として認められるための旅立ちなのであり、従って戻ってくることが前提の別離なのである。それでいて、「そーか。結局は親父の跡を継ぐんだな」みたいなこと考えてしまう私のような人間にさえ、ここでの「別離」がひじょうな切なさで迫ってくるのは、なぜなんだろう。
それは、この時彼が別れていくのがたんに故郷の町ではなく、美登利や正太、長吉といった幼馴染たちでもなく、子ども時代そのものだからだ。彼らと居られた至福の時間、そのものだからだ。
水仙の作り花を格子の隙間からさし入れて、顔も見ないで立ち去った——。
それが、信如の精一杯の美登利への気持ちであることが分かるようになっていたら、その人はもう、子どもではない。
信如は後に、どのような僧侶になったのだろう。市井の塵にうづもれつつ、私もまた幼き日を想う。
手元にあるのは→岩波文庫2004年改版8刷。他にやはり遊郭に材を取った「にごりえ」を収める。詳細な「注」付。
『ayus vol.74』2006年10月発行より
文学の中に感じる仏教を、アーユス会員の瀬野美佐さんが綴るエッセイ。
瀬野美佐(せの・みさ)三重県の曹洞宗寺院に生まれる。駒沢大学仏教学部卒業後、曹洞宗宗務庁に勤務。[共著]『仏教とジェンダー』『ジェンダーイコールな仏教をめざして』(いずれも朱鷺書房)猫好きの山羊座。アーユス会員。





