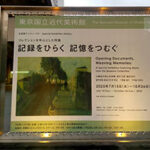
今月26日まで東京国立近代美術館で「コレクションを中心とした特集 記録をひらく 記憶をつむぐ」展が開催中です。展示の中核になっているのは「戦争記録画」。第二次世界大戦中、日本の陸海軍は当時の中堅画家たちへ、前線の兵士たちの活躍を国内に伝える絵画の制作を依頼しました。描かれた作品は当時、「聖戦美術展」「大東亜戦争美術展」などで全国を巡回し、多くの観客を集め、国内の戦意高揚に貢献しました。そのように人びとが戦争に向かい、戦争の当事者となっていく経緯をも知らせる作品群は、現在の世情を考える上でも非常に示唆に富むものです。今こそ観られるべき展示と思います。
これらの作品は終戦直後に米軍に接収されましたが、1970年に「無期限貸与」として返還されました。しかしこれらは美術による「戦争協力品」と見做されることとなります。画家の作品リストから外されることもめずらしくありません。藤田嗣治が日本国籍を捨ててフランスに渡ったのは戦争画を描いたことへの批判を嫌ってと言われています。戦争画がタブーでなくなるのは、21世紀を待たなければなりませんでした。
今回の展示会は大規模なものなのに、チラシもカタログも作られませんでした。それは戦争画が未だにタブーなゆえか、と思いきや、理由はただ、「予算がなかった」から。同館が所属する独立行政法人国立美術館への国の運営交付金は年々減額されており、限られた予算の中で、今回は内容を重視し、すべての展示に英文解説を付けるなどに予算を充てたとのこと。学芸員の志を褒めるとともに、この国の貧しさを心配します。
既成仏教教団が自らの戦争責任を問えるようになったのは戦後50年、1995年以降です。加えてこの10年ほどは近代仏教の研究が大変盛んになり、改めて仏教者の戦争責任と戦後責任が問われています。遅すぎた取り組みとも見えますが、一方で、単なる糾弾や反省ではない、多角的な検証ができるのが今だとも言えます。排外主義が伸長しつつある今にとるべき態度を考える上でも必要なことです。
そして、現在まさに起きている戦争の現場に思いを馳せます。原因を辿ると、植民地時代の課題が解決されないまま、今まで引きずっているものも少なくありません。NGOも、活動地の課題が、どう過去の戦争の影響を受けているのか、あらためての検証は大切と思います。
「記録をひらく 記憶をつむぐ」展はそれを丁寧に実践しています。ぜひご体験ください。今月26日まで。